アースウォッチ・トークスとは
アースウォッチの運営に携わる多彩な役員や、活動を指導してくださっている研究者の皆様による講演プログラムです。生物多様性の保全にどう関わるかなど、各々の専門と体験から語っていただくシリーズです。
SDGsのターゲット「13. 気候変動に具体的な対策を」、「14. 海の豊かさを守ろう」、「15. 陸の豊かさも守ろう」について具体的な活動例を、野外活動の意義や楽しさも含めて紹介、2022年のCOP15で決定された「2020年以降の生物多様性に関する世界目標」に関する話題を紹介など、多岐にわたる内容をお楽しみいただきながら、アースウォッチの活動や理念の特長をご理解ください。
第十九回 2026年1月30日(金)19:00-20:00
「富士山周辺の絶滅危惧チョウ類」の成果報告
富士山生物多様性研究室・甲州昆虫同好会 渡邊 通人
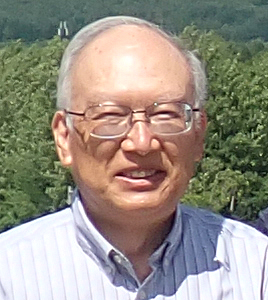 渡邊 通人(わたなべ みちひと)先生
渡邊 通人(わたなべ みちひと)先生
25年間高等学校理科教諭を務めた後、河口湖フィールドセンター自然研究室長、副館長、館長を歴任し、都留文科大学非常勤講師(生態学)を務めた。2012年よりNPO法人富士山自然保護センター理事兼自然共生研究室長。2022年からは「富士山生物多様性研究室」を開設して調査研究活動を継続し、日本鱗翅学会会長を3年間務めた。
「富士山周辺の絶滅危惧チョウ類」プロジェクトは2003年から2012年まで、富士山北麓の梨ケ原、高座山草原、野尻草原、本栖高原で、渡邊通人先生のご指導の下開催されました。2006年からの2年間は国際プロジェクトとしても開催し、国内では延べ約260人のボランティアが調査を手伝いました。渡邊先生が、これらの調査を含む富士山麓の調査結果を論文にまとめられ、「蝶と蛾」に発表されました[1,2]。今回は、論文の内容をご共有頂くとともに、その後のご研究内容等もお話しいただきます。
日本の里山的自然のひとつである草原環境は生活様式や産業構造の変化に伴い、採草地としての需要がなくなり草刈りや火入れ等が行われなくなったことで、森林への遷移が急速にすすんでいます。このため、草原環境保全のkey-speciesとして絶滅危惧種でもある草原性チョウの生態調査を行いました。絶滅に瀕している原因を追求するとともに、草原環境全体の推移を見守り保全策を策定するための基礎調査と位置付けられます。
アースウォッチのプログラムでは毎年4~10月に定期的に行われたチョウ類全体の調査の一部を、マーキング、写真撮影、記録などで手伝いました。ボランティアはミヤマシジミ、アサマシジミ、ヒョウモンチョウの幼虫の食餌植物の分布と食痕や共生アリの探索と記録、成虫の捕獲とマーキングと記録等を行いました。
[1] 渡邊通人“富士山麓半自然草原における絶滅危惧種コウゲンヒョウモンの地域個体群構造”,蝶と蛾73(3/4)p.93-110(2022)
[2]渡邊通人 “草原性絶滅危惧種アサマシジミのメタ個体群構造”, 蝶と蛾 76(3) p.97-125 (2025)
渡邊先生からのメッセージ
富士山は日本一の高山で、その優美な姿は多くの人々を魅了してきました。しかし、観光資源としての開発や観光客の増加、生活様式の変化、地球規模の気候変動など様々な要因から、その自然環境は大きな影響を受け変化しています。中でも、草原環境の減少とその質の変化から草原性絶滅危惧動植物の生育生息が脅かされているのが現状です。富士山は、生物多様性ホット・スポット日本の中央に位置し、日本全体の約半数の生物種が生育生息する、日本全体の生物多様性維持の鍵をにぎる地域でもあります。
そこで、富士山北麓の草原性絶滅危惧種であるミヤマシジミ、アサマシジミ、コウゲンヒョウモン、ヒメシロチョウを対象とした保全生態学的調査を、アースウォッチ・ボランティアの皆様のご協力を頂き、環境省の「生物多様性保全上重要な里地里山」に選定されている「富士山北麓の草原」である梨ヶ原、高座山草原、野尻草原、本栖高原の4つの半自然草原で、2003年から10年間実施しました。その中で様々な新発見があり、それぞれの種の地域個体群構造や生活特性、それに火入れや草刈りなどの人為作用がどのように関わっているかがみえてきました。
今回は、これらの調査から判ってきた各絶滅危惧種の生活の様子と、人との関わりの大切さをご紹介したいと思います。
申し込み:Zoomによるオンライン形式(無料、事前申し込み制)
次回 2026年4月を予定
