アースウォッチ・トークスとは
アースウォッチの運営に携わる多彩な役員や、活動を指導してくださっている研究者の皆様による講演プログラムです。生物多様性の保全にどう関わるかなど、各々の専門と体験から語っていただくシリーズです。
SDGsのターゲット「13. 気候変動に具体的な対策を」、「14. 海の豊かさを守ろう」、「15. 陸の豊かさも守ろう」について具体的な活動例を、野外活動の意義や楽しさも含めて紹介、2022年のCOP15で決定された「2020年以降の生物多様性に関する世界目標」に関する話題を紹介など、多岐にわたる内容をお楽しみいただきながら、アースウォッチの活動や理念の特長をご理解ください。
第十八回 2025年9月19日(金)19:00-20:00
「若狭小浜のシロウオ」
福井県立大学海洋生物資源学部先端増養殖科学科教授 富永 修
福井県立若狭東高等学校教諭 松井 明
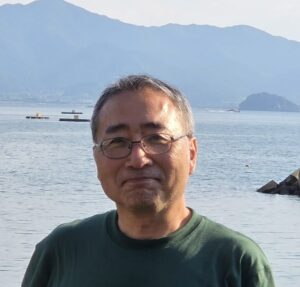 富永 修(とみなが おさむ)先生
富永 修(とみなが おさむ)先生
福井県立大学海洋生物資源学部 先端増養殖科学科 教授
地下水・湧水が沿岸海域の生物生産や生物多様性に作用する仕組み、資源回復や自然再生をテーマにした研究に従事。専門は水圏資源生物学、水産増養殖科学。
 松井 明(まつい あきら)先生
松井 明(まつい あきら)先生
福井県立若狭東高等学校 教諭、小浜市いさざ採捕組合 組合長
魚類や水生昆虫の分布を調査し、望ましい河川整備や圃場整備のあり方を研究。専門は、河川・水田生態学、応用生態工学。
シロウオ(Leucopsarion petersii)は、踊り食いなどの生食で知られるスズキ目ハゼ科の魚です。太平洋側・日本海側の各地で行われるシロウオ漁は、川岸に組んだ「やぐら」から四手網や袋網を使って捕獲する伝統的な方法で、地域の文化として受け継がれています。若狭地方でシロウオは「イサザ」と呼ばれ、福井県小浜湾では、毎年3月になると産卵のために河川を遡上し、その姿は春の訪れを告げる風物詩として親しまれてきました。
しかし近年、河川改修などによって産卵場である砂礫底が失われ、遡上する数は大幅に減少しました。現在では環境省の絶滅危惧Ⅱ類に指定されています。さらに漁業者の高齢化も進み、シロウオ漁はほとんど見られなくなりました。その結果、近くの川にシロウオが生息することを知らない人も増え、十分な保全対策がとられないまま、この魚は姿を消してしまうかもしれません。
そこで、このたびアースウォッチでは、「若狭小浜のシロウオ」調査を立ち上げました。この調査により、河川での親魚の遡上や産卵の様子を調べ、孵化後に海へ下った仔魚のすみかを探し出し、減少の原因を明らかにしていきます。
今回のトークスでは、若狭地方におけるシロウオの現状と、これからの研究についてお話を伺います。多くの方のご参加をお待ちしています。
富永先生からのメッセージ
知らないことに関心をもつことはできません。まずは、知ることから始まります。ただ、知っていることと、できることは違います。さらに、できるからといって、物事の本質を理解できているかと言えば、そうとも限りません。
本取り組みに参加される皆さんは、環境問題や地域活性に関心が高い方たちと思います。皆さんには、シロウオ調査を通して、常に「なぜ」、「なに」と思考していただき、私たちと一緒に調査・研究を進めていただければと思います。
シチズン・サイエンティストとしての皆さんの好奇心と探求心が、シロウオ復活の原動力になると信じています。
楽しみ、考え、議論しましょう。みなさんの参加をお待ちしています。
申し込み:Zoomによるオンライン形式(無料、事前申し込み制)
次回 2026年1月を予定
